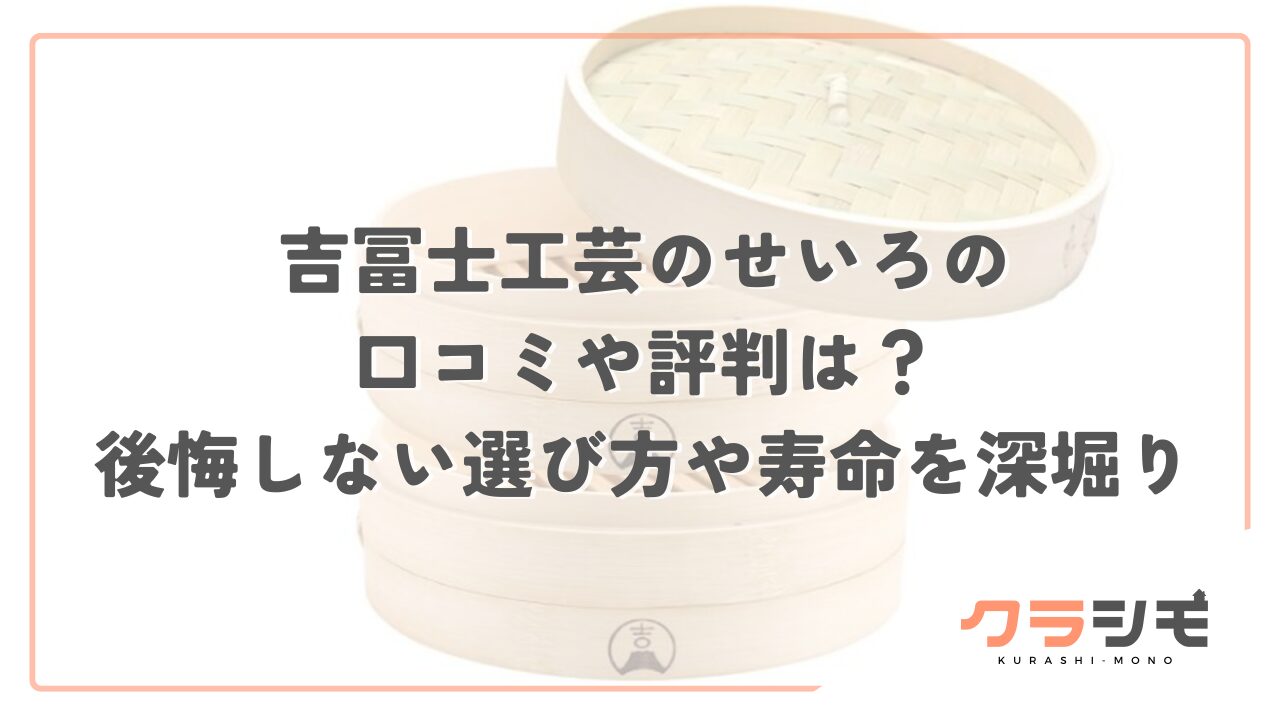リーズナブルな価格で人気の「吉冨士工芸」のせいろ。購入を考えている方のなかには、「評判はどう?」「使い勝手はいい?」と悩む方もいるはずです。
そこでこの記事では、吉冨士工芸の口コミ・評判を徹底調査し、良い面や悪い面をわかりやすくまとめました。
また、原産国や寿命、安全性、そして「何センチが良いのか」など、知っておくべき情報も網羅しました。
せいろがあると、お家の食事がぐっと豊かになります。ぜひ、購入の参考にしてもらえると嬉しいです。
- 吉冨士工芸せいろのリアルな口コミと評判
- あなたに最適なせいろのサイズ選び
- 初心者でも分かる正しい使い方とお手入れ方法
- 長く愛用するためのカビ対策と寿命の目安
吉冨士工芸のせいろの口コミと評判を徹底調査
- 吉冨士工芸せいろの悪い口コミ
- 吉冨士工芸のせいろの良い口コミ
- 結局何センチがいい?サイズの選び方
- 初心者向け!吉冨士工芸せいろ21cmの特徴
- 家族で使える吉冨士工芸せいろ24cmの特徴
吉冨士工芸せいろの悪い口コミ
まず最初に、吉冨士工芸のせいろに関する悪い口コミをチェックしていきましょう。購入前にはデメリットや注意点についても正確に理解しておくことは重要です。

※画像はせいろのイメージです
ネガティブな口コミで最も多く見られるのは、日本製ではなく中国製であることに対する書き込みが多い印象です。
日本製のセイロを探していたのでこの商品を選びましたが、写真に撮った説明書きの右下に「MADE IN CHINA」と書かれてあり驚きました。日本の会社である吉富士工芸制で職人が一つひとつ手で編んだものと書かれてあれば、消費者は日本製だと思ってしまう。そこが残念でした。中国製であるならきちんと購入時に分かるようにしておくべきです。また、初めて使用した際に、セイロに横にひび割れが出来ましたが、その後も使用は出来ています。
引用元:Amazonより抜粋
他には、品質の個体差に関する指摘も一部で見られます。
二つ注文しましたが、一つが難ありでした。やはり使用してみると壊れました。LINEで業者さんに連絡すると素早い対応していただき再送していただけました。安心して注文出来るメーカーです。
引用元:Amazonより抜粋
購入後空蒸しをした時点で、繋ぎ目の部分が剥がれてしまいました。その後問題なく使えていますが、値段相応かと思いました。
引用元:Amazonより抜粋
工業製品のように寸分の狂いもなく均一、というわけにはいかないのが、天然素材を用いた手仕事に近い製品の特性でもあります。
多くの場合、使用上の問題はありませんが、完璧な商品を求める場合は、こうした特性をあらかじめ理解しておく必要があります。
購入前に知っておきたいポイントは、以下の通りです。
- 日本製ではなく中国製
- 品質の個体差
- 耐久性に関する注意
天然素材のため、使用後の乾燥を怠るとカビが発生しやすいという点は最も重要な注意点です。また、工業製品とは異なり、竹の編み目や色合いに若干の個体差が生じる場合があります。
急激な温度変化や乾燥はひび割れの原因となりうるため、丁寧な取り扱いが製品の寿命を左右します。
吉冨士工芸のせいろの良い口コミ
では次に、吉冨士工芸のせいろに関する良い口コミを見ていきましょう。

※画像はせいろのイメージです
ムラのなさに感動しました。竹の香りもいい感じだし。ちょこちょこ使います。野菜もたくさん蒸しました。めちゃくちゃ美味しかったです。
引用元:Amazonより抜粋
温野菜したいと思って漸く買いました。野菜の甘みヤバい。本来の野菜の美味しさが分かります。買って良かった!手入れも簡単です。
引用元:Amazonより抜粋
手作りシュウマイなど料理の幅が広がりました。
引用元:Amazonより抜粋
思ったより小さいかなという感じでしたが、使いやすいです。
引用元:Amazonより抜粋
買って良かった!せいろを楽しむために、野菜色々と豚肉、胡麻ダレ等を購入。そして仕事から帰宅し、野菜を切り、お肉を乗せれば、出来上がり。この夏場に時短で出来る夕食がどんなに有り難いことか、、、。
次の日は明太子マヨと焼売を購入し、タレの味変も加わり、またまた美味しくいただく。こんなに楽だとは、、、野菜も沢山食べれるし、ヘルシー。
引用元:Amazonより抜粋
最初の使用時、水洗い空蒸しを15分したが、その時作った料理はセイロの木の香りが移ってしまい…失敗!! 出来れば30分程はした方が良い
ですが、ほぼ毎日晩御飯で大活躍♡美味しくヘルシーな食事を楽しんでおります。お腹にも心にも大満足です。
引用元:Amazonより抜粋
多くのユーザーに選ばれている理由は、食材が持つ本来のポテンシャルを最大限に引き出す、優れた調理性能です。
他にも、「普段食べている野菜が、驚くほど甘く、そして濃い味わいになった」「冷凍の肉まんやシュウマイが、電子レンジとは全くの別物。お店で出てくるような、ふっくらもちもちの食感に仕上がる」といった口コミもありました。
口コミから見える魅力をまとめると、以下の通りになります。
- 食材の味を格上げする
- 本格的な仕上がり
- 食卓を彩るデザイン性
- 効率的な同時調理
素材の味が引き出されるだけでなく、冷凍食品でさえ専門店のような本格的な仕上がりになります。
また、見た目の美しさから、調理後そのまま食卓に出せる点も好評です。
さらに、多くの製品が2段式のため、主菜と副菜を一度に調理できる効率の良さも、忙しい現代のライフスタイルにマッチしていると言えます。
結局何センチがいい?サイズの選び方
吉冨士工芸のせいろを選ぶ上で悩むのは、サイズ選びではないでしょうか。
せっかく手に入れても、サイズが合わなければ「思ったより入らなかった」「大きすぎて持て余してしまう」といった事態になりかねません。
後悔しないために、せいろのサイズは「普段食事をする人数」と「主に作りたい料理のイメージ」という2つの軸で検討するのが、失敗しないためのコツです。

※画像はせいろのイメージです
吉冨士工芸では、家庭での使用を想定した18cmから、少し大きめの27cmまで、複数のサイズがラインナップされています。
それぞれのサイズがどのようなシーンで活躍するのか、以下の詳細な比較表で具体的にイメージを掴んでみましょう。
| サイズ | 人数の目安 | 主な用途の具体例 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 18cm | 1〜2人 | 肉まん1〜2個、一人分の温野菜、茶碗蒸し1個、点心2〜3個 | 一人暮らしや二人暮らしに最適。既存の小鍋にも合わせやすいが、調理できる量は限定的 |
| 21cm | 2〜3人 | 肉まん2〜3個、切り身魚と付け合わせ野菜の同時調理、2合分のもち米 | 最も汎用性が高く、初心者に一番おすすめのサイズ。「大は小を兼ねる」が通用しにくいせいろにおいて、最初の1台として間違いのない選択肢 |
| 24cm | 3〜4人 | 肉まん3〜4個、家族分の主菜、中サイズの魚の姿蒸し、複数の器を並べたプリン作り | 家族での使用がメインならこのサイズ。調理の幅が広がるが、家庭用の鍋には合わない場合も。購入前に鍋の直径確認が必須 |
| 27cm | 4〜5人以上 | 一度に大量の点心を蒸す、おもてなし用の大きな料理、お赤飯やちまき作り | 本格的な料理や大人数での使用を想定したサイズ。収納場所の確保と、サイズに合う大きな鍋が必要になる上級者向け |
サイズ選びで迷ったら
どのサイズにするか迷った場合、あるいは明確な使用目的がまだ定まっていない場合は、まずは21cmから試してみるのが最も賢明な選択と言えます。
汎用性と扱いやすさのバランスが絶妙で、「せいろの基本」を学ぶのに最適です。
大きすぎないため、蒸気が効率よく全体に回り、加熱ムラも起きにくいという利点もあります。
大は小を兼ねない理由
調理器具選びでは「大は小を兼ねる」と考えがちですが、せいろの場合は必ずしもそうとは言えません。
例えば、大きなせいろで少量の食材を蒸そうとすると、空間が広すぎて蒸気が分散し、かえって加熱に時間がかかったり、うまく蒸し上がらなかったりすることがあります。
初心者向け!吉冨士工芸せいろ21cmの特徴
前述の通り、せいろ初心者の方には21cmサイズが最適です。
その理由は、まず使い勝手の良さにあります。2〜3人家族の食事にちょうど良い大きさで、主菜と付け合わせの野菜を2段で同時に調理する、といった使い方が可能です。

引用画像:Amazonより
例えば、下の段で豚バラ肉を蒸し、上の段で野菜を蒸せば、一度で栄養バランスの取れた一食が完成します。
収納時も場所を取りすぎず、気軽にせいろ生活を始められます。
21cmサイズがおすすめな理由
ご飯であれば約2合分を炊くことも可能です。蒸して作るおこわなどは格別の美味しさで、料理のレパートリーが広がります。
家族で使える吉冨士工芸せいろ24cmの特徴
3〜4人以上の家族で使いたい場合や、一度にたくさんの量を調理したい方には24cmサイズが適しています。

引用画像:Amazonより
24cmの魅力は、調理容量の大きさです。
例えば、家族全員分のシュウマイを一度に蒸したり、大きな魚を丸ごと一匹蒸す「姿蒸し」のような、食卓が華やぐ料理にも挑戦できます。茶碗蒸しなども、複数の器を並べて作ることが容易です。
ただし、サイズが大きくなる分、ご家庭の鍋に乗るかどうかを事前に確認する必要があります。せいろの底が鍋の縁にしっかり乗るのが理想的な状態です。
合う鍋がない場合は、せいろと鍋がセットになった商品を選ぶと間違いありません。
吉冨士工芸のせいろの口コミ以外の情報
- 原産国は日本製?中国製?
- 天然素材だから気になる安全性
- 竹製と杉製はどちらがよい?
- 初心者でも安心な使い方
- 寿命と長く使うお手入れ
- カビさせない正しいお手入れ方法
原産国は日本製?中国製?
吉冨士工芸は、熊本県に本社がある日本の企業「Phase株式会社」が運営するブランドです。
国内のメーカーが企画・販売しているという点は、製品を選ぶ上での一つの安心材料になるでしょう。品質管理や顧客対応への期待も高まります。
ただし、製造元は日本製というわけではないようです。せいろやIH対応鍋、ステンレス製の蒸し板など、中国で製造されているものが多いです。
天然素材だから気になる安全性
口に入れるものを調理する器具だからこそ、安全性は最も気になるところです。吉冨士工芸のせいろは、その点でも配慮がされています。
まず、主たる素材は天然の竹や杉であり、化学的な処理は最小限に抑えられています。さらに、人体に有害な蛍光剤などは使用されていません。
これは、食品に直接触れる調理器具として非常に重要なポイントです。

※画像はせいろのイメージです
また、せいろは構造上、いくつかの部品を接着剤で固定している箇所があります。
この接着剤についても、食品に触れても問題がない、食品衛生法の基準をクリアしたものが使用されています。
高温の蒸気で加熱調理するという特性上、使用の都度、殺菌されるため衛生的に使い続けることが可能です。
竹製と杉製はどちらがよい?
吉冨士工芸では、主に竹製と杉製のせいろが扱われています。それぞれに特徴があり、どちらを選ぶかは好みや用途によって異なります。
どちらが一方的に優れているというわけではなく、ご自身の好みやせいろをどのように使っていきたいかというライフスタイルによって、最適な選択は異なります。
両者の特性を深く理解し、比較検討することが、満足のいく「せいろ選び」への第一歩です。
竹製せいろ
竹製のせいろは、優れた耐久性とコストパフォーマンスから、多くのメーカーでスタンダードな素材として採用されています。
「初めてのせいろ」として最も推奨されることが多いタイプです。
竹は繊維が緻密で弾力性に富むため、頻繁な使用や洗浄にも耐えうる丈夫さを持っています。
また、素材自体の香りが非常に控えめであるため、食材が持つ繊細な香りを邪魔することがありません。
肉や魚、野菜など、ジャンルを問わずどんな食材とも相性が良く、まさに「万能選手」と呼ぶにふさわしい存在です。
日常の食卓で気兼ねなく、毎日使いたいと考える方には、竹製が最適でしょう。
杉製せいろ
杉製のせいろは、蓋を開けた瞬間にふわっと立ち上る、杉特有の清々しく高貴な香りが最大の魅力です。
この豊かな香りは、食材、特にご飯ものや蒸しパンなどに移り、料理をワンランク上のものへと昇華させてくれます。
料亭で出てくるような、香り高いおこわや茶碗蒸しを家庭で再現したいと考える、食通の方にはたまらない選択肢です。
また、吸湿性にも優れており、よりふっくらと仕上げる効果も期待できます。
ただし、繊細さゆえに、竹に比べると耐久性はやや劣り、価格も高価になる傾向があります。香りを楽しむための特別な道具として、大切に扱いたい上級者向けの素材と言えるかもしれません。
| 比較項目 | 竹製せいろ(吉冨士工芸の主力) | 杉製せいろ |
|---|---|---|
| 耐久性 | ◎:非常に丈夫で、日常使いに適している | △:デリケートで、丁寧に扱う必要がある |
| 香り | △:香りは控えめ。食材の香りを活かせる | ◎:杉特有の上品な香りが楽しめる |
| 価格 | ○:比較的安価で、手に入れやすい | △:高価な製品が多い |
| 得意な料理 | 肉、魚、野菜、点心など、オールマイティ | おこわ、蒸しパン、白身魚など、香りを活かす料理 |
| おすすめな人 | 初心者、日常的に幅広く使いたい方 | 料理好き、木の香りを楽しみたい上級者 |
初心者でも安心な使い方
「せいろ」と聞くと、どこか専門的で扱いが難しそう、というイメージをお持ちの方もいるかもしれません。
しかし、いくつかの基本的なルールさえ押さえれば、誰でも簡単・安全に美味しい蒸し料理を作ることができます。

※画像はせいろのイメージです
まず、せいろが届いたら、すぐにでも何かを蒸したくなる気持ちをぐっとこらえ、最初に行うべき非常に重要な準備作業があります。それが「空蒸し(からむし)」です。
空蒸しの手順と目的
空蒸しとは、文字通り、食材を何も入れずにせいろ本体を蒸す作業のことです。これを行うことで、せいろは調理器具として最適な状態に整えられます。
- 全体を水で濡らす
まず、せいろ本体と蓋を流水でさっと濡らします。
- 鍋にセットして蒸す
次に、ご家庭の鍋にお湯を沸かし、湯気が十分に上がったら、濡らしたせいろを乗せて蓋をします。
- 10〜15分間、蒸気を当てる
この状態で、10分から15分ほど、蒸気で全体を蒸し続けてください。
- 風通しの良い場所で乾燥
時間が来たら火を止め、せいろを鍋から下ろし、風通しの良い日陰で内側も外側も完全に乾くまで干します。
この一手間をかける目的は、主に3つあります。
- 竹や木が持つ特有の匂いを和らげる
- 木材に水分を含ませて耐久性を高める
- 衛生的な状態にする
初回準備が完了すれば、いよいよ日々の調理でせいろを使っていきます。基本的な使い方は、以下の4つのステップで完結します。
【準備】使用前に全体をさっと濡らす
調理を始める前に、必ずせいろ本体と蓋を流水で濡らしてください。
この工程は、食材の匂いが木に移るのを防ぐと同時に、鍋の水が万が一空焚き状態になった際に、せいろが焦げ付くのを防ぐための重要なコーティングの役割を果たします。
【保護】クッキングシートや葉物野菜を敷く
次に、せいろの底(すのこの部分)に、クッキングシートや蒸し料理用の専用シートを敷きます。あるいは、キャベツや白菜、レタスといった葉物野菜を敷くのも大変おすすめです。
これは、食材がすのこにくっついてしまうのを防ぎ、肉や魚から出る余分な脂が直接木に染み込むのを防ぐためです。結果として、後片付けが格段に楽になります。
【配置】食材は詰め込みすぎない
食材をせいろの中に並べる際は、「蒸気の通り道」を意識することが最大のコツです。
食材同士がぎゅうぎゅうに重なり合っていると、蒸気がうまく循環せず、加熱ムラができてしまいます。
特に2段で調理する場合は、熱が通りにくい根菜や肉類を、より蒸気が強い下の段に置くと効率的です。
【加熱】湯気がしっかり上がってから乗せる
鍋のお湯が完全に沸騰し、湯気が勢いよく立ち上っているのを確認してから、食材を入れたせいろを鍋に乗せます。
火加減は、湯気の勢いが弱まらない程度の中火から強火を維持し、調理中はお湯がなくならないように時々確認しましょう。
寿命と長く使うお手入れ
吉冨士工芸のせいろの寿命は、使用頻度と日頃のお手入れ次第で大きく変わります。適切に扱えば数年以上にわたって愛用することが可能です。
長持ちさせるための最大のポイントは、前述の通り「使用後にしっかりと乾燥させる」ことです。
天然の竹は水分を含んだままだと、劣化やカビの原因となります。洗った後は、必ず風通しの良い日陰で、完全に乾くまで干してください。
また、耐久性については、竹製は杉製よりも高いとされていますが、強い衝撃を与えたり、急激な乾燥(直射日光や食器乾燥機の使用)は、ひび割れの原因になるため避けるべきです。
丁寧に扱うことが、結果的に寿命を延ばすことに繋がります。
寿命を縮めるNG行動
- 洗剤を使ってゴシゴシ洗う
- 食器洗い乾燥機で洗浄・乾燥させる。
- 濡れたままビニール袋などに入れて保管する。
- 直射日光に当てて乾かす。
合成洗剤は、竹が本来持つ天然の油分や抗菌成分まで洗い流してしまい、かえって劣化を早める原因となります。
また、食器洗い乾燥機の高温洗浄と乾燥は、歪みや割れの直接的な原因となり、絶対に使用してはいけません。
そして、濡れたままビニール袋など通気性の悪い場所で保管することは、カビを発生させる最も危険な行為です。
カビさせない正しいお手入れ方法
せいろを使う上で最も避けたいのが「カビ」の発生です。しかし、正しい予防法と対処法を知っていれば、過度に心配する必要はありません。
カビの予防方法
カビを防ぐ基本は、すぐに洗い、完全に乾かすことです。
- 使用後は、熱いうちにお湯か水でさっと洗い流します。汚れがこびりついている場合は、たわしなどで優しくこすり落としましょう。基本的に洗剤は使いません
- 洗い終わったら、清潔な布巾で水気をよく拭き取ります。
- 風通しの良い場所で、立てかけるなどして陰干しし、内側も外側も完全に乾燥させます。湿気の多い場所での保管は避けてください。
万が一カビが生えてしまったら
もし黒い点々(初期のカビ)を見つけても、諦めるのはまだ早いです。軽度なものであれば対処可能です。
まず、消毒用エタノールを吹きかけて拭き取ります。その後、80℃以上のお湯を10秒以上かけることで熱湯消毒します。
処置が終わったら、再び風通しの良い場所で完全に乾燥させてください。これでも落ちない頑固なカビは、残念ながら落とすのが難しい場合があります。
まとめ:吉冨士工芸のせいろの口コミや評判は?後悔しない選び方や寿命を深堀り
いかがでしたか?この記事では、吉冨士工芸のせいろの口コミを詳しく解析し、購入前に気になる疑問点を網羅的に解説してきました。
実際の利用者による吉冨士工芸せいろの口コミからは、食材の味が格段に向上する一方で、お手入れには注意が必要であることがわかります。
せいろは正しく使えば長く愛用できる優れた調理器具です。あなたの食卓をより豊かにするパートナーとして、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
- 吉冨士工芸は熊本の会社が運営する日本のブランド
- せいろ本体は主に中国製で天然竹が使用されている
- 蛍光剤不使用など安全性に配慮した作りになっている
- 良い口コミでは食材が美味しくなるという声が多数
- 野菜は甘く、肉はふっくらジューシーに仕上がる
- 悪い口コミではお手入れの手間やカビへの懸念が挙げられる
- 製品の品質には天然素材ゆえの個体差がある場合も
- サイズ選びは1〜2人なら18cm、2〜3人なら21cmが目安
- 初心者やサイズに迷う人には21cmが最もおすすめ
- 3人以上の家族なら24cm以上が便利
- 使い方は初回に空蒸しをし、使用前は水で濡らすのが基本
- お手入れは洗剤を使わず水洗いし、しっかり陰干しする
- 寿命は使い方次第で、適切なお手入れで長く愛用できる
- カビ対策は使用後すぐに洗い、完全に乾燥させることが最も重要
- 手頃な価格で本格的な蒸し料理を楽しめる入門用に適した製品