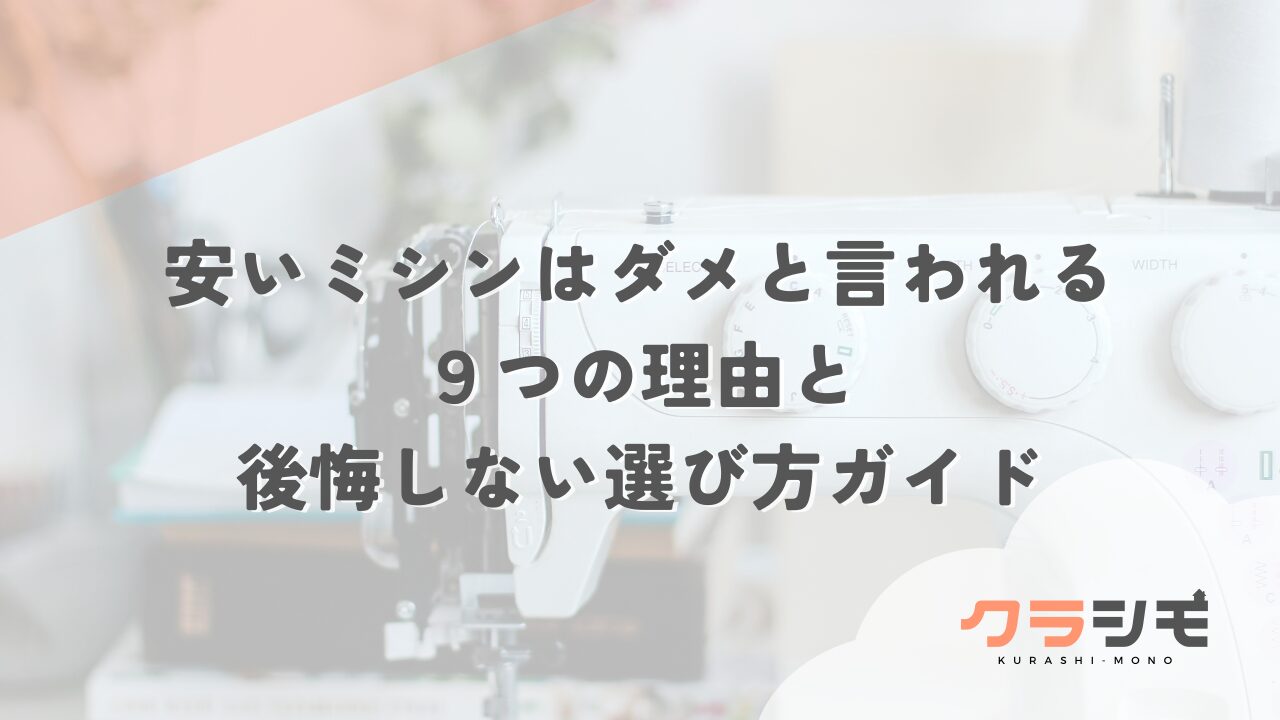「買ってはいけないミシンの特徴を知りたい」
「安いミシンは壊れやすい?実際どう?」
ミシンを購入する場合、「安いミシンはダメ?」と疑問に思うのではないでしょうか。とくに初心者の方は、低価格のモデルに惹かれるはずです。
そこでこの記事では、安いミシンはダメと言われる理由をお伝えしながら、後悔しないミシン選びのポイントを分かりやすく解説します。
結論から言うと、安いミシンは耐久性や使いやすさに問題がある場合が多く、選び方を間違えると後悔する可能性があります。
価格だけでなく機能やメーカーの信頼性を重視することが大切です。
初心者におすすめのモデルもご紹介します。
- 安いミシンの耐久性や使いやすさに関する課題
- 初心者が後悔しないミシン選びのポイント
- 安価なミシンと高価なミシンの性能や機能の違い
- 各種ミシンの特徴や用途に応じた選び方
安いミシンはダメと言われる9つの理由
- 部品がプラスチック製で耐久性が低い
- モーターが弱く厚物縫いに対応できない
- 生地送りが不安定で縫い目が乱れる
- 糸調子が手動で調節が難しい
- 振動が大きく縫製時にズレやすい
- 修理対応が難しく部品交換が困難
- 軽量すぎて安定性に欠ける
- 縫える布地の種類や厚さに制限がある
- 価格を抑えるために機能や性能が限定的
部品がプラスチック製で耐久性が低い
安いミシンは、部品にプラスチックが多用されていて、軽量化やコスト削減が行われています。その結果、耐久性に問題が出やすくなります。

特にギアや内部構造の重要部分がプラスチック製の場合、摩耗や破損が起きやすく、長時間使用には向きません。
また、プラスチックは経年劣化で脆くなるため、ミシンの寿命が短くなりがちです。
モーターが弱く厚物縫いに対応できない
安価なミシンは、小型で出力の低いモーターが使われていることが多いです。そのため、厚手の生地や重ね縫いには対応できない場合があります。
モーターの性能不足は、縫製中の停止やスムーズな生地送りを妨げる原因になります。
また、長時間使用すると過熱しやすく、これが故障や寿命短縮につながります。
生地送りが不安定で縫い目が乱れる
安価なミシンは、生地送り機構(フィードドッグ)の品質が低いため、生地送りにムラが発生しやすくなります。
その結果、縫い目の間隔にズレが出やすく、仕上がりに影響を及ぼします。特に薄手や伸縮性のある素材では問題が顕著です。
また、生地送り機構自体の摩耗も早く、性能低下につながる場合があります。
糸調子が手動で調節が難しい
糸調子は、縫い目の仕上がりに直結する重要な要素です。しかし、安価なミシンは精度が低く、適切な調整が難しい場合があります。
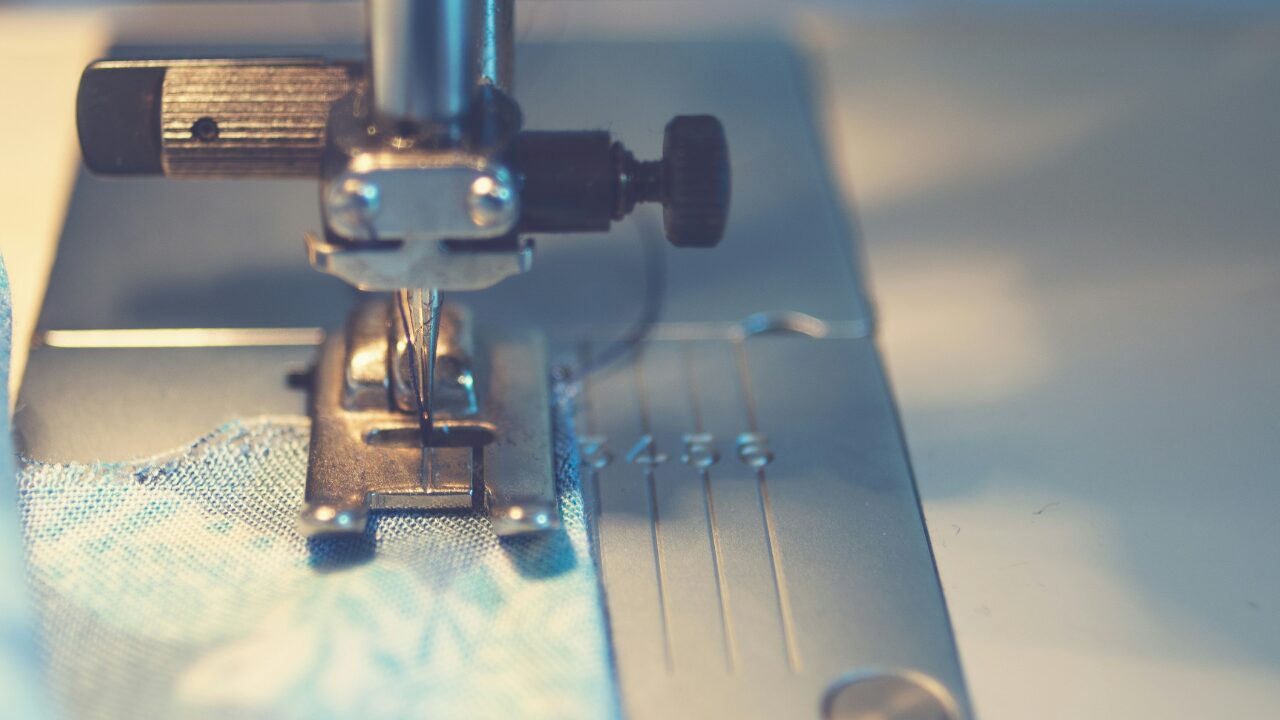
初心者にとって、手動の調整はハードルが高く、不均一な縫い目や糸絡みなどのトラブルにつながることがあります。
また、生地や糸の種類ごとに細かく調整する必要があり、経験者でも手間取ることがあります。
振動が大きく縫製時にズレやすい
安価なミシンは、振動が大きく縫製中に生地がズレやすいという問題があります。
軽量設計や内部部品の精度不足が原因で縫い目が不均一になり、仕上がりに影響する可能性も考えられます。
修理対応が難しく部品交換が困難
安価なミシンは、修理対応や部品交換が難しい場合があります。
特殊な部品を使っていたりサポート体制が整っていないと、修理費用が高額になる可能性も考えられます。
故障した場合は、新しいミシンを購入した方が安く済むケースもあります。

また、安価なミシンは保証期間が短く、1年未満の場合もあります。
修理費用は自己負担になることもあり、保証があったとしても、主要パーツ以外は対象外の場合も考えられます。
軽量すぎて安定性に欠ける
安価な軽量ミシンは、持ち運びや収納には便利ですが、使用時の安定性に欠ける場合があります。
縫製中に振動で動いたり、生地がズレて縫い目が乱れることがあります。
また、軽量化されたミシンは内部部品の強度が低い場合も多く、耐久性にも影響します。
縫える布地の種類や厚さに制限がある
安価なミシンは、縫える布地や厚さに制限があります。
薄手の生地には対応できても、デニムなど厚手の布地ではモーターや針が力不足になる場合があります。
また、伸縮性のある素材や滑りやすい布地にも対応できないモデルが多いです。
価格を抑えるために機能や性能が限定的
安価なミシンはコスト削減のため、自動糸調子や自動糸切りなど便利な機能が省略されていることがあります。
ステッチパターンも少なく、高度なデザイン作りには不向きです。
また、高速縫製やボタンホール作成機能も簡易的で、中級者以上には物足りなく感じる場合があります。
何がダメ?後悔しない安いミシン選びのポイント
- 買って良かったミシンを選ぶための基準
- 壊れにくいメーカーの特徴とおすすめブランド
- いつ購入するのがお得?安く買えるタイミング
- 初心者におすすめの安いミシンとは?
- プロがすすめる最強のミシンとは?
買って良かったミシンを選ぶための基準
ミシンを選ぶ際には、使いやすさや機能性、耐久性など、いくつかの重要な基準を考慮することが大切です。

どんな用途でミシンを使うのかを明確にする
まず、自分がどのような用途でミシンを使うのかを明確にしましょう。
例えば、初心者は基本的な直線縫いやジグザグ縫いができれば十分ですが、経験者や多機能を求める方はステッチの種類や自動糸調子機能なども重視する必要があります。
簡単に操作できるか確認する
例えば、糸通しがスムーズであることやボビンのセットが簡単であることは、初心者にとって大切なポイントです。
また、フットペダルの感度や速度調整機能があると、作業がより快適になります。
重さやサイズを確認する
ミシンの重さやサイズも考慮しましょう。持ち運びが必要な場合は軽量モデルを選び、自宅で固定して使う場合は安定感のあるモデルがおすすめです。
価格と品質のバランスを考える
安いミシンは価格面では魅力的ですが、先にお伝えしたように耐久性やサポート体制に問題がある場合があります。
一方で、高価なモデルは多機能ですが、自分の用途に合わない場合は宝の持ち腐れになってしまう可能性もあります。
壊れにくいメーカーの特徴とおすすめブランド
壊れにくいミシンを選ぶためには、信頼できるメーカーを選ぶことも大切です。有名ブランドは、長年の実績と高い評価があり、一般的に耐久性や品質が優れています。

おすすめのブランドとしては、例えば、「ブラザー(Brother)」や「ジャノメ(Janome)」「ジャガー(Jaguar)」が挙げられます。
初心者向けからプロ仕様まで幅広いモデルを販売しており、使いやすさと信頼性で知られています。
また、「Juki」や「Bernina」は高耐久性と精密な縫製性能でプロフェッショナルにも支持されています。
他にも、「Pfaff」や「Husqvarna Viking」なども高品質なミシンを作っており、多機能モデルや工業用ミシンを探している方には特に適しています。
いつ購入するのがお得?安く買えるタイミング
ミシンをお得に購入するには、タイミングを見極めることも重要です。
一年の中でも特定の時期にはセールやキャンペーンが行われることが多く、このタイミングで購入すると割引価格で手に入れることができます。
- ブラックフライデー
- サイバーマンデー
- 年末・クリスマスセール
などが大規模なセール期間です。
また、夏の終わりから秋口にもセールが行われることがあります。この時期は新モデルが発表されるタイミングでもあり、旧モデルが割引される傾向があります。
| セール名称 | 期間 |
|---|---|
| ブラックフライデー | 2024年11月29日(金) |
| サイバーマンデー | 2024年12月2日(月)〜12月8日(日) |
| 年末セール | 2024年12月中旬〜12月31日 |
| 新春セール | 2025年1月1日(元日)〜1月7日 |
| 春のセール | 2025年3月中旬〜3月末 |
| 夏のセール | 2025年7月中旬〜7月末 |
| 秋のセール | 2025年10月中旬〜10月末 |
一般的なセール期間ではない場合でも、楽天市場などでは独自のセールが行われていることもあります。
安いだけじゃない初心者におすすめのミシン4選
初心者向けのミシンは、使いやすさや機能性が重視されます。ここでは、特におすすめのモデルをご紹介します。
ジャノメ JN860
ジャノメ JN860は、初心者でも扱いやすい設計のコンピューターミシンです。
自動糸調子機能があり、ボタン一つで糸の調整が可能です。多様な縫い模様も搭載されており、様々な縫い方に対応できます。
ブラザー SENSIA 135
ブラザーのSENSIA135も初心者に人気のモデルです。
自動糸通し機能や、簡単に操作できるタッチパネルが特徴で、初めての方でもスムーズに使えます。特に、布の厚さに応じた調整がしやすい点が評価されています。
ジャガー MM-222I
ジャガーのMM-222Iは、シンプルな操作性が魅力です。
基本的な縫い方をマスターするのに適しており、コストパフォーマンスも良好です。特に、軽量で持ち運びがしやすい点が初心者にとって大きな利点です。
ブラザー PS202
ブラザーのPS202は、初心者に優しい設計がされたモデルです。
自動糸調子機能や、簡単に操作できるボタン配置が特徴で、初めての方でも安心して使用できます。
多彩な縫い模様があり、さまざまな作品に対応可能です。
本当にダメ?安いミシンを買う前に知るべきポイント
- 買ってはいけないミシンの特徴
- 安いミシンは壊れやすい?
- 小型ミシンのデメリット
- 家庭用ミシンの寿命はどれくらい?
- ミシンは重いほうが良い理由とは?
- 電子ミシンとコンピューターミシンの違い
- コンピューターミシンの欠点に注意
- 職業用ミシンと家庭用ミシンの違い
買ってはいけないミシンの特徴
ミシンを選ぶ場合、「初心者が避けたほうが良いポイント」というものがあります。ここでは、買ってはいけないミシンの主な特徴を挙げます。

厚手の生地が縫えないミシン
安価なミシンやコンパクトなミシンのなかには、パワー不足のため、厚手の生地を扱うことができない機種もあります。
使用時にストレスを感じたり、思ったような仕上がりにならないことがあるため注意が必要です。
プラスチック製の部品が多いミシン
多くの部品がプラスチック製のミシンは、熱や衝撃に弱く、すぐに歪んだり割れたりする可能性があります。これにより、長期間の使用が難しくなるため注意しましょう。
ハンディタイプのミシン
片手で操作できるハンディタイプのミシンは、手軽に見えて初心者には難易度が高いことが多いです。
また、重さや安定性の面で問題もあり、思うように縫えない可能性があります。
機能が制限されているロックミシン
安すぎるロックミシンは、機能やできることが制限されているため、特定の用途にしか使えないことがあります。

糸の本数によってできることが変わるため、用途に合った選択が重要です。
評判の悪いブランド
信頼性の低いブランドや、口コミで評判の悪いミシンは避けるべきです。特に、修理やサポートが不十分な場合、長期的に見て不便を感じることが多いです。
これらの特徴を考慮しながら、自分のニーズに合ったミシンを選ぶことが大切です。
欲しい機能が付いていない
必要な機能が備わっていないミシンは、初心者にとっては非常に不便です。
例えば、自動糸調子機能がないと、糸の調整を手動で行う必要があり、縫い物が難しくなります。自分の目的に合った機能があるかどうかを確認することが重要です。
価格が安すぎるミシン
安価なミシンは、初心者向けとされることが多いですが、実際は機能や耐久性が不足していることが多いです。
安いミシンは壊れやすい?
すべての安いミシンがそうとは言えませんが、安価なミシンは品質や部品の都合上、壊れやすい可能性はあります。

安価なモデルではプラスチック製の部品が多用されており、金属製に比べて耐久性が劣ります。これにより、長時間使用すると摩耗や破損が起こりやすくなります。
また、モーターの出力が低いため、厚手の生地やデニムなどを縫う際に負荷がかかり故障するケースもあります。
安価なミシンは短期間で使用する場合には適していますが、本格的な裁縫や長期使用を考えている場合には不向きです。
購入時には価格だけでなく、性能や耐久性も考慮することが重要です。
小型ミシンのデメリット
小型ミシンは軽量でコンパクトなため、収納や持ち運びが便利です。しかし、その反面、いくつかのデメリットがあります。

力不足の可能性
まず、サイズが小さい分、モーターの出力が弱いことが多く、厚手の生地や複数枚重ねた布を縫う際には力不足になることがあります。
どのため、用途が限定されてしまい、本格的な裁縫には向かない場合があります。
安定性に欠ける
小型ミシンは安定性に欠けることも課題です。軽量なため縫製中に振動が大きくなり、生地がズレたり縫い目が乱れる原因となります。
耐久性への影響
さらに、内部部品が簡易的な素材で作られている場合、耐久性が低く、故障しやすい傾向があります。このような問題は長期間使用する際に特に影響を及ぼします。
家庭用ミシンの寿命はどれくらい?
家庭用ミシンの寿命は、使用頻度やメンテナンスによって異なりますが、一般的には10年から15年程度と言われています。

安価なミシンや小型モデルは、部品の耐久性が低いため寿命が短い場合があります。
プラスチック製の内部部品は摩耗しやすく、頻繁に使うと3~5年程度で故障することもあります。
定期的なメンテナンスが大切
ただし、定期的なメンテナンスや適切な使用方法が大きく影響します。
例えば、使用後にホコリを取り除いたり、定期的にオイルを差すことで寿命を延ばすことができます。
寿命を延ばすためには、信頼できるメーカーの製品を選び、取扱説明書に従った使い方を心掛けることが大切です。
定期的に点検をすることで、不具合を早期に発見でき長く使うことができます。
ミシンは重いほうが良い理由とは?
ミシン選びは、重量も重要なポイントです。重いミシンは安定性という大きな利点があります。

軽量モデルでは縫製中に振動で動いてしまうことがありますが、重いミシンはしっかりと固定されるため、生地送りがスムーズになり縫い目も均一になります。
安定性は厚手の生地や長時間の作業時に役立ちます。
自宅で固定して使うなら重いミシンがおすすめ
また、重いミシンは内部構造にも違いがあります。多くの場合、金属製のフレームや部品を使用しており、耐久性と精度が高いです。
重いミシンは、持ち運びが不便というデメリットはあります。ただし、自宅で固定して使用する場合には安定性と耐久性を優先するほうがおすすめです。
電子ミシンとコンピューターミシンの違い
電子ミシンとコンピューターミシンは、操作性や機能面で異なります。

電子ミシンの特徴
電子ミシンは針の動きを電子回路で制御し、速度調整や針停止位置の設定が可能です。
模様選択はダイヤル式で、ステッチの種類や細かい調整機能は限られています。そのため、基本的な裁縫作業には十分ですが、複雑なデザインには不向きです。
コンピューターミシンの特徴
一方、コンピューターミシンは内蔵されたコンピューターで動作を制御します。
液晶ディスプレイやボタン操作によってステッチパターンを簡単に選択でき、多様な模様縫いや刺繍も可能です。
また、自動糸切りやエラー表示などの便利機能も搭載されており、安全性と精度が高い点が特徴です。
ただし価格は高めであり、初心者には操作が複雑に感じられる場合もあります。
コンピューターミシンの欠点に注意
コンピューターミシンは多機能で便利ですが、いくつかの欠点があります。
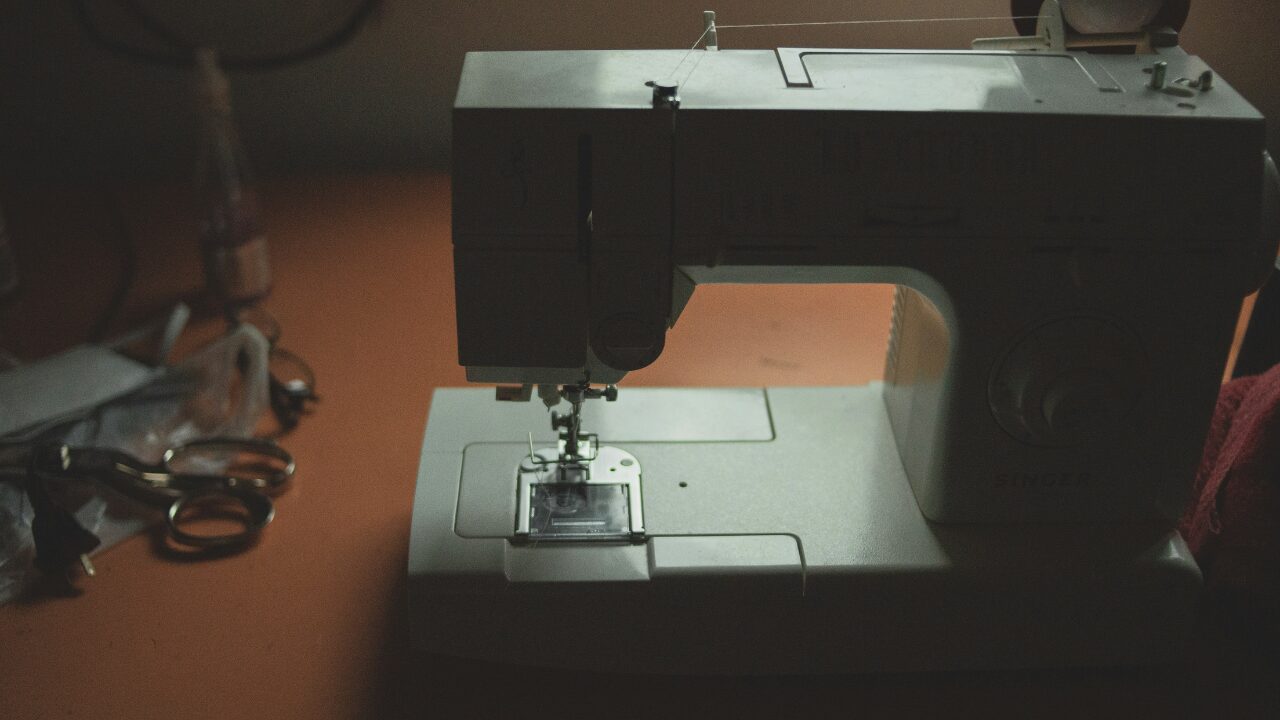
価格や修理費用が高額
最大のデメリットは価格です。電子ミシンや電動ミシンと比べて高価であり、高性能モデルでは数十万円になることもあります。
また、内部にコンピューター基板を搭載しているため、故障時には修理費用が高額になる可能性があります。
操作が複雑
操作が複雑と感じる人もいます。デジタル表示や多くのボタン操作に慣れるまで時間がかかり、初心者には使いこなすまでにハードルがある場合があります。
電源と耐久性の問題
また、電源が必要なため停電時には使用できず、一部モデルでは耐久性が低いという声もあります。
職業用ミシンと家庭用ミシンの違い
職業用ミシンと家庭用ミシンには、用途や性能において大きな違いがあります。

職業用ミシンの特徴
職業用ミシンは直線縫い専用で、パワフルなモーターと高い回転数が特徴です。毎分1300~1600針のスピードで縫えるため、大量の布地を短時間で仕上げることが可能です。
また、金属製のボディや部品が多く使用されており、耐久性に優れています。一方で、模様縫いやボタンホール縫いなどの装飾的な機能はほとんどありません。
家庭用ミシンの特徴
家庭用ミシンは、多機能性が特徴です。直線縫いだけでなく、ジグザグ縫いやボタンホール縫いなど、多様なステッチが可能です。
モーターの出力は職業用に比べて控えめですが、軽量で持ち運びや収納がしやすい設計になっています。初心者でも扱いやすく、趣味や日常的な裁縫に適しています。
最後に:安いミシンはダメな理由と後悔しない選び方まとめ
いかがでしたか?
安いミシンはダメと言われる理由について、部品の耐久性からアフターサポートまで詳しく解説しました。
安いミシンはダメな点が多いものの、予算や用途に応じて適切なモデルを選べば、初心者でも快適に使用できます。
ミシン選びでは、価格だけでなく、必要な機能や耐久性、メーカーのサポート体制なども考慮に入れることが大切です。
この記事を参考に、後悔しないミシン選びをしていただければ幸いです。
- 部品にプラスチックが多用され耐久性が低い
- モーターの出力が弱く厚手の生地に対応できない
- 生地送りが不安定で縫い目が乱れる
- 糸調子の調整が難しく初心者には扱いづらい
- 振動が大きく縫製中に生地がズレやすい
- 修理対応が難しく部品交換が困難
- 保証期間が短くアフターサポートが不十分
- 軽量設計で安定性に欠ける
- 縫える布地や厚さに制限がある
- 機能や性能が価格を抑えるために限定されている
- 厚手の布地や特殊素材への対応力が不足している
- 長時間使用すると過熱し故障しやすい
- ステッチパターンの種類が少なくデザイン性に欠ける
- アフターサポート体制が整っていないブランドも多い
- 初心者には操作性や耐久性において不向きな場合が多い